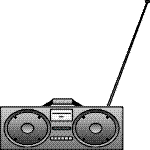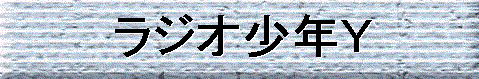
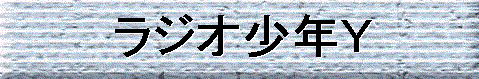
近頃ラジオ少年という言葉はもはや死語となったが、昭和30年代の少年の何人かに一人はラジオに興味を持ってい た。ラジオと言っても、聞くのがメインで はなく、作るのである。
 少年Yは昭和30年代に入ってすぐラジオに興味を持ち、自分で作りたいと思うようになった。ただし、模型屋で売っているラジオの組み立てキットは少年の
小遣いに比べて高く、毎日模型屋のガラスの棚に並んでいる組み立てキットを眺めて通るのが日課となっていた。
少年Yは昭和30年代に入ってすぐラジオに興味を持ち、自分で作りたいと思うようになった。ただし、模型屋で売っているラジオの組み立てキットは少年の
小遣いに比べて高く、毎日模型屋のガラスの棚に並んでいる組み立てキットを眺めて通るのが日課となっていた。
当時、内田某という人がラジオ少年向けに本を何冊か出しており、少年Yはその本を何度も何度も読み返して早くラジ
オを作りたいと思っていた。
少年Yの家はそれほど裕福ではなかった。というよりも、昭和30年前後は裕福な家庭はほんの一部だった時代である。少年Yの小遣いは月に300円くらい
だった。一日10円といったところだ。それに比べてラジオの組み立てキットは600円か700円で、少年Yは、駄菓子屋で菓子を買うのも2ヵ月ほど我慢し
て、ラジオの組み立てキットを買うためのお金を積み立てた。当時は現在の飽食の時代からは想像もつかないくらい食料事情も良くなくて、駄菓子屋で菓子を買
うのを我慢するのはかなりつらかったようであった。
小学校高学年の少年にとっては長い2ヵ月だった。ようやくラジオの組み立てキットを買うお金ができて、その大事な
お金を握りしめて、模型屋に走って行き、ゲルマニュームダイオードを使ったラジオの組み立てキットを買って帰った。
組み立てるにはハンダごてが必要だが、とてもハンダごてまで買う余裕はないし、そのために小遣いを新たに積み立てるほど少年Yには忍耐力が残っていな
かった。そこでどうしたか?
少年Yは、台所から七輪を庭に持って出て(その頃はまだ少年Yの家にはガスコンロはなくて、ようやく石油コンロが登場した時代だった)、木炭で火を起こ
し、鉄製の火箸の先を真っ赤に焼いて、父親の家庭大工道具箱の中にあった脂(ヤニ)入りはんだを使って数カ所のハンダ付けを行った。火箸を焼いてはハンダ
を付け、また焼いてはハンダを付けて、長い時間をかけてラジオはようやく完成した。
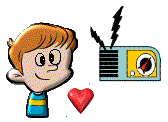 アンテナはその日に備えて、隣のアパートの屋上からビニール被覆の導線を引っ張ってきていた。アンテナをつなぐ前にクリスタルイヤホーンを耳に入れてみ
たが当然音はでない。でも、少年Yには何か聞こえるような感じがした。いよいよアンテナにつなぐ。少年の胸は心臓が飛び出るほどドクンドクンと音がした。
アンテナにつながった線の先の被覆を剥いて、今組み立てたばかりのラジオのアンテナ端子につないだ。カリカリという音がした。まだ放送は聞こえない。今と
違って、放送局もそんなに多くない。ラジオの同調のつまみを廻すとかすかに音が聞こえてきた。そのときの少年Yは、全身が聴覚になっていた。つまみを廻し
て音が大きくなるように調整する。はっきりと聞こえてきた。鳴った、鳴った。もう夢中だった。あとは、アースを取るともっと聞こえると内田某の本に書いて
あったので、地面に銅線を埋めてアースを取った。前よりも良く聞こえた。
アンテナはその日に備えて、隣のアパートの屋上からビニール被覆の導線を引っ張ってきていた。アンテナをつなぐ前にクリスタルイヤホーンを耳に入れてみ
たが当然音はでない。でも、少年Yには何か聞こえるような感じがした。いよいよアンテナにつなぐ。少年の胸は心臓が飛び出るほどドクンドクンと音がした。
アンテナにつながった線の先の被覆を剥いて、今組み立てたばかりのラジオのアンテナ端子につないだ。カリカリという音がした。まだ放送は聞こえない。今と
違って、放送局もそんなに多くない。ラジオの同調のつまみを廻すとかすかに音が聞こえてきた。そのときの少年Yは、全身が聴覚になっていた。つまみを廻し
て音が大きくなるように調整する。はっきりと聞こえてきた。鳴った、鳴った。もう夢中だった。あとは、アースを取るともっと聞こえると内田某の本に書いて
あったので、地面に銅線を埋めてアースを取った。前よりも良く聞こえた。
学校から帰ると自分で作った自分だけのラジオを聞くのが少年Yの日課になった。内田某の本を何度も読んだ。する と、もう少し高級なラジオが作りたくなった。それでもトランジスタを使ったラジオはずいぶん高価だったので、実現したのはずっと後のことだった。
このゲルマニュームラジオは、電源が不要である。
この頃一般的な携帯用のラジオといえば、真空管からトランジスタに移る頃だったと思う。考えられないだろうが、真空管を電池で動かすのである。真空管に
は電球と同じくフィラメントがあり、このフィラメントを灯す電池がA電池で1.5V、高圧の電源用がB電池で67.5Vだったようだ。内田某の本には、野
球場で携帯ラジオを聴いている人を対象に、「え〜電池、え〜電池」とA電池を売っていたと書いてあった。懐中電灯をつけっぱなしにしているようなもので、
電池の寿命も、今から考えると数分の一しかなかったと考えられる。
次に、少年Yはロッドアンテナを買って、ラジオにつけ、近くの4階建てのアパートの屋上に行って、ラジオを聞い
た。市内に放送局があったので、電波がよく届き、ゲルマニュームラジオでも結構大きい音で聞こえた。
少年は、高ければ高いほど電波が強いと考え、近くの山に登ることを考えた。山といっても海抜200メートルそこそこの山である。にぎり飯を風呂敷に包ん
で、腰にしばり、途中で小さな小川の水を飲みながら頂上に着いた。さっそくラジオを聞いてみた。アパートの屋上よりもっとよく聞こえた。ガンガンと鳴っ
た。Yはうれしくて、山の尾根をラジオを聞きながら歩いた。自分で作った自分だけのラジオを持って、たぶん鼻唄を歌っていたようだ。それから何回か山に
登った。何回かに一回は友達も誘った。
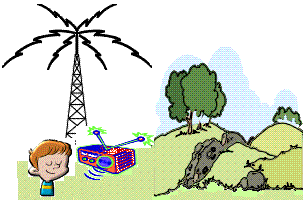
中古の5球スーパのラジオを手にしたラジオ少年Yは、まずこれを分解して部品レベルにしてしまう。分解するときに ハンダに残っている脂(ヤニ)の臭いがなんとなく技術の臭いがして、Yはいっぱしの技術者のような顔をしていた。小さな部品、例えば抵抗とかキャパシタ は、ハンダをはずしてリード線を一応まっすぐにしておいた。キャパシタは、ペーパコンデンサという種類で、ワックスが含浸してあり、まわりにほこりがつき やすかった。
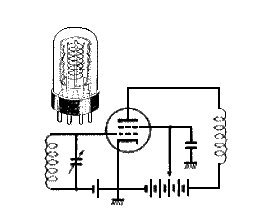 部品を外すときには、回路図を書きながら、部品の定数を書き込んでいくのである。当時の5球スーパは、ほとんど回路が固定されていた。ラジオを作ってい
る会社には回路設計者などは必要なかったのではあるまいか。
部品を外すときには、回路図を書きながら、部品の定数を書き込んでいくのである。当時の5球スーパは、ほとんど回路が固定されていた。ラジオを作ってい
る会社には回路設計者などは必要なかったのではあるまいか。
このころには中学生になっていた少年Yのレベルでも、ラジオの回路が書けたのである。完全に分解したあと、シャーシと呼ばれたアルミの台に真空管のソ
ケットとか電源トランスとかを組み立てていく。それから配線を始める。最初はヒータの配線を青いビニール線で行う。配線の色はJISで決められていた。少
年が作るラジオにJISを適用する必要もないが、あとで故障したときに、間違って高圧を触ることがないように、彼は配線の色をきちんと守っていた。高圧は
250Vくらいあった。ヒータの配線は二本を撚っていなければならない。今でいうツイストペアーというところだ。これは、ハム音といって、交流の50ヘル
ツとか60ヘルツの音が信号に混ざるのを防ぐためだと、先の内田某の本に書いてあった。ヒータの電圧は6.3Vだった。当時の真空管のシリーズの前のシ
リーズは2.5Vで、真空管の名前も数字二桁だった。例えば,6D6は昔58と呼んでいた。
ヒータの配線が終わると、それから順番に他の配線をしていく。ハンダの境界が線材となす角が滑らかでないとハンダ
の接続品質がおちることも少年Yはその頃覚えた。そのころのハンダは、ずいぶん太い脂(ヤニ)入りハンダだった。ハンダが溶ける際に脂の臭いがプンプンし
て、部屋の中が臭かった。配線が終わると、回路図と合わせていく。これは、今のLSIの設計のときにもLVS(Layout Versus
Schematics)といって配線間違いを防ぐ大事な工程の一つである。
そしていよいよ電源を入れる。最も緊張する一瞬である。配線間違いがあると、瞬間にヒューズが飛ぶ場合とか、真空管が真っ赤になるとか、きな臭い臭いが
してくるとか、いろんなケースがある。音がでるとまず安心であるから、Yは、電源を入れるとまず音を聞いた。音が出ないとすぐ電源を切る。そしてまた
LVSをやるわけである。真空管が真っ赤になっても、配線を正してやり直すと、正常に動く。昔はのんびりしたものである。後で経験したトランジスタなら、
そんなことはない。瞬時に壊れる。
少年Yにとって、5球スーパはあまりアマチュアの臭いがしなかった。作れば市販のラジオと同じ音がでる。でもそれ
だけだった。やはりアマチュアの香りがするのは、再生式というラジオで、真空管は1本とか2本しか使わない。それでスピーカから音がでる。内田某の本に
は、戦時中はこの再生式ラジオが主流だったとか書いてあった。
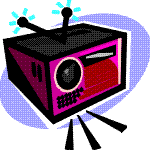 再生というのは、ポジティブフィードバックすなわち正帰還を施しているのである。少ない部品で感度を上げるために、いったん増幅した信号を、再度入力に
加えるのである。例えば、10倍の増幅回路に、5%だけもう一度入力に戻してやると、20倍になる。そんな原理である。この方式は元々不安定であるから、
この5%の量をその都度調整する必要があった。ピ〜、キュワ〜ンといった音を立てながら安定して大きく聞こえる点で止めてやる。近くに別のラジオがある
と、そのラジオからも同じピ〜という音が聞こえてくる。今の電波規制なら当然パスしない。このラジオはYにとっては、かなりアマチュアの香りがするもの
だった。調整ツマミにつながっている可変キャパシタ(バリコンと呼んでいた)が高圧につながっているので、誤ってシャーシの内側のバリコンを触ると感電し
てしまうのである。
再生というのは、ポジティブフィードバックすなわち正帰還を施しているのである。少ない部品で感度を上げるために、いったん増幅した信号を、再度入力に
加えるのである。例えば、10倍の増幅回路に、5%だけもう一度入力に戻してやると、20倍になる。そんな原理である。この方式は元々不安定であるから、
この5%の量をその都度調整する必要があった。ピ〜、キュワ〜ンといった音を立てながら安定して大きく聞こえる点で止めてやる。近くに別のラジオがある
と、そのラジオからも同じピ〜という音が聞こえてくる。今の電波規制なら当然パスしない。このラジオはYにとっては、かなりアマチュアの香りがするもの
だった。調整ツマミにつながっている可変キャパシタ(バリコンと呼んでいた)が高圧につながっているので、誤ってシャーシの内側のバリコンを触ると感電し
てしまうのである。
当時は少ない部品で性能を上げることが雑誌にも掲載されていた。再生式をさらに極端にしたものが超再生式というも のである。最近の女子高生の得意の言葉の「チョー」である。手で調整するのをやめて、帰還量を増やして、そうすると不安定になるから強制的に戻してやる、 そしてまた帰還を始める。要するに、帰還を断続的に切ったりつないだりしているのである。これは驚くべき性能を持っていた。FMでもAMでも受信できた。 昔のトランシーバはほとんどこの方式だったようだ。
そのほかには、リフレックス方式というのがあった。一つの真空管でまず高周波増幅を行い、検波して低周波になった 信号をもう一度最初の真空管に戻してやる。一つの真空管で高周波と低周波の二つの信号を増幅するのである。高周波増幅1段、検波、低周波増幅1段というの は、昔アマチュアが1V1と呼んでいたものである。Vの前が高周波、後が低周波で、0V1とか1V2とか表していた。それが真空管1本で1V1が出来るわ けである。音も十分大きかった。
 少年Yも大きくなって、高校受験の年を迎えた。ラジオに関する興味はますます強くなり、深夜まで内田某の本や、ほかにもラジオの製作、無線と実験等、今
でも存続している雑誌を読んでいた。少年Yの両親はあまり勉強のことをやかましく言わなかった。深夜、Yの父親がトイレか何かに起きたときに内田某の本を
まだ読んでいたYに対して、「お前は何をしているのか。ラジオ屋の丁稚になるなら今のままでもいい。上に進むならやることをきちんとやれ」と叱った。これ
が少年Yにとって、父親に勉強のことで叱られた最初で最後だったようだ。そのときから、Yは、深夜までラジオの本を読むのは止めにした。当時は父親の権威
もあったし、今に比べれば、子供もずいぶん素直だったものだ。
少年Yも大きくなって、高校受験の年を迎えた。ラジオに関する興味はますます強くなり、深夜まで内田某の本や、ほかにもラジオの製作、無線と実験等、今
でも存続している雑誌を読んでいた。少年Yの両親はあまり勉強のことをやかましく言わなかった。深夜、Yの父親がトイレか何かに起きたときに内田某の本を
まだ読んでいたYに対して、「お前は何をしているのか。ラジオ屋の丁稚になるなら今のままでもいい。上に進むならやることをきちんとやれ」と叱った。これ
が少年Yにとって、父親に勉強のことで叱られた最初で最後だったようだ。そのときから、Yは、深夜までラジオの本を読むのは止めにした。当時は父親の権威
もあったし、今に比べれば、子供もずいぶん素直だったものだ。
その後、彼は高校に進み、クラブ活動で物理部に入り、ラジオいじりを続けた。1年まではラジオ少年だったが、さすがに2年、3年になると、成績の低下が
気になって、ペースは落としたようだ。
大学は電子工学科だった。回路の中心はまだ真空管で、講義も真空管中心だった。若手の助教授の講義でトランジスタ が登場したが、古手の教授は真空管からトランジスタへの切り換えができない様子がYには分かった。トランジスタの回路の講義などは、最前列に座り、先生の 間違いを探すイヤミな学生だった。彼は大学でも回路が好きだった。この頃はさすがにトランジスタを使うことが多くなっていた。塩化第二鉄の溶液を買ってき て、自分でプリント配線板も作った。ジャンク屋で計算機のプリント板の中古を買ってきて部品を外して使ったりした。トランジスタのリードが短くて、再利用 しづらかったのをYは今でも覚えている。トランジスタの名前は、確か2SC132だったようだ。
いまや少年Yは50歳を過ぎているが、幸いにも会社でずっと回路をやってきた。回路の内容は少年時代から大きく変 化したが、三つ子の魂ではないが、今でも回路が好きな模様である。回路に向かったときの彼の眼は、10歳の少年Yと何も変わらない。変わったことといえ ば、ハンダ付けするには、視力が衰えたことである。それと、世の中にラジオ少年がいなくなったことに対するぼやきが増えたことくらいか・・・・・